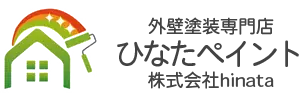【奈良県外壁塗装】外壁塗装したばかりなのに気泡が…徹底解説|奈良県奈良市の外壁・屋根・屋上塗装業者|ひなたペイント
- 【奈良県外壁塗装】外壁塗装したばかりなのに気泡が…徹底解説
- 2025/07/14
- 外壁塗装

-
せっかく新しい外壁塗装を終え、鮮やかな仕上がりに胸を弾ませていたのに、数日〜数週間で“プツプツ”と小さな気泡(ブリスター)が現れてしまうと、とてもショックですよね。今回は 「外壁塗装直後に気泡が出てしまう理由」 と 「どのように対処・予防すれば良いか」 を、わかりやすくまとめました。気泡のメカニズムを知れば、業者に適切な相談ができるだけでなく、今後のメンテナンス計画にも役立ちます。
1.気泡(ブリスター)とは?
気泡とは、塗膜下に閉じ込められた空気や湿気が膨張し、塗料の表面が小さく盛り上がる現象です。見た目が悪いだけでなく、塗膜が破れると防水性・耐久性が一気に低下し、早期の剥離やひび割れへとつながります。
2.外壁塗装直後に気泡が発生する主な原因
-
下地の含水率が高かった
施工前の水分量測定が不十分で、乾燥が不十分なまま塗装すると、水蒸気が内部に残り気泡を押し上げます。 -
下塗り材・上塗り材の相性不良
速乾型シーラーの上に溶剤系塗料を重ねるなど、メーカーが推奨しない組み合わせの場合、化学反応で発泡することがあります。 -
気温・湿度・施工タイミング
真夏の直射日光下や梅雨時の高湿度環境では、塗膜内の溶剤が急激に揮発し、逃げ場のないガスが気泡化しやすくなります。 -
施工不良(攪拌不足・塗布量過多)
塗料を充分に攪拌せずに塗った、あるいは一度に厚塗りし過ぎた場合、内部に空気が巻き込まれて残ってしまいます。
3.発見したときのチェックポイント
- 発生範囲と数:局所的か全面的かで原因が絞れます。
- 発生時期:施工直後なら材料・気候要因、半年以上後なら経年劣化の可能性。
- 押してみる感触:柔らかい場合は水蒸気、硬い場合はガスや溶剤残留が疑われます。
4.早めの対処が肝心!推奨される処理手順
-
施工店にすぐ連絡
施工保証期間内であれば無償補修の対象になるケースがほとんど。発生箇所を写真で記録し、状況を共有しましょう。 -
気泡部の除去と再塗装
軽度ならサンドペーパーで膨れを削り、下地調整後に部分補修。広範囲なら全面ケレン+再塗装が必要です。 -
含水率測定と乾燥養生
補修前に必ず水分測定器で下地湿度を確認し、必要なら送風機などで充分に乾燥させてから再塗装します。
5.再発を防ぐためのポイント
- 施工前の下地調査を徹底:含水率10%以下が目安。
- 気象条件を見極める:気温5〜35℃、湿度85%未満の日を選択。
- メーカー仕様書を厳守:塗布量、攪拌時間、乾燥時間の順守で化学反応トラブルを防止。
- 二回塗りで乾燥時間確保:一度に厚塗りせず、インターバルを守る。
6.業者選びで確認したいチェックリスト
- 含水率計や赤外線温度計を使用しているか
- 塗料メーカーの認定施工店か
- 施工後に写真付きの完了報告書を提出してくれるか
- 最低でも3〜5年の工事保証があるか
7.まとめ
外壁塗装直後の気泡は「施工不良?」と不安になりますが、正しい原因特定と的確な補修で十分リカバー可能です。ひなたペイントでは、下地含水率の二重チェックや気象データを基にした施工計画を徹底し、仕上がり後のアフターフォローも万全。もし気泡を見つけたら「早期発見・早期連絡」が鉄則です。
施工店と協力し、長期的に美観と耐久性を維持していきましょう。
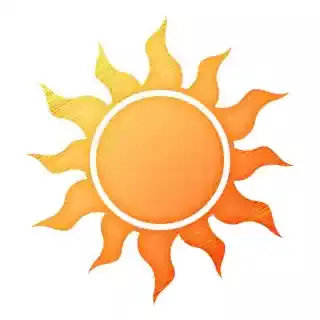
-
下地の含水率が高かった